科学的根拠は信頼できるのか?再現性から考える情報の見極め方
情報の信憑性を精査する際に、何を基準に判断しているでしょうか?
現在では、科学に基づいているかが重要な基準です。
科学に基づいていれば、この情報は正しいと判断する人は多いです。SEOですらも、科学的根拠があればいい記事と判断するほどです。
しかし、そんな科学にもフィクションの世界が存在します。
今回は科学は絶対に正しいものではないをテーマに、信頼できる科学について見ていきましょう。
科学がフィクションとはどういうことか?
そもそも科学とは何かというと、真実に限りなく近づこうとする学問です。
これだけを聞くと、情報の信憑性を判断するのに最も適していると言えるでしょう。
しかし、注意しなければならないことがあります。
Science Fictions あなたが知らない科学の真実では、科学は絶対的に正しいものではないと警鐘を鳴らしています。
著書では、多くの科学論文を読んで結果を再現してみると、ほとんどの論文が再現不可能だったと述べられています。
世界的な学術誌である「ネイチャー」、「サイエンス」の論文の再現性ですら62%でした。
6割ほどは信憑性を確保できるが、残り4割は信憑性に疑問があります。
特に心理学では、再現性の低さに問題があるとされます。その例として、ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンが主張したプライミング効果というものがあります。
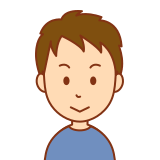
プライミング効果とは、事前に見たり聞いたりした刺激が、その後の行動や思考に影響を与える現象のことです。
プライミング効果を実際に行えるか再現すると、ほとんどの実験で事前に受けた刺激による影響を受けなかったことが報告されています。
ダニエル・カーネマン本人も、プライミング効果は誇張しすぎたと述べています。
私たちが科学に対して持っている印象は、絶対的に正しいというイメージです。
しかし、実際は全てが絶対的に正しいのではなく、一部は限りなく真実に近い情報で信憑性があり、一部は再現不可能な信憑性のない情報が述べられています。
一見、研究では物事が上手く証明されているように見えても、蓋を開ければフィクションのように作り込まれている可能性があります。
なぜ科学にフィクションが生まれるのか?
それは科学を行っているのが人間であるということ。
真実に限りなく近づこうとする学問に、人間の欲や事情が混入することでフィクションが生じます。
欲や事情とうのは、承認欲求や研究をしていくための資金などいかにも人間らしい要因によるものです。
科学界で問題となる具体的な例は詐欺、誇張、過失、補助金問題、研究の意義が関わっています。それぞれの内容を見ていきます。
科学界でいう詐欺は、みなさんもご存じのSTAP細胞の事件が該当します。論文に使用するデータを偽造作成して、あたかも新しい発見をしたかのように見せる。
残念ながら、科学の世界でも定期的に詐欺事件が起こります。
それと似たような件として、誇張があります。誇張は実験の結果を大げさに盛って、発表してしまうことです。
なぜこのようなことが起きるかと言うと、研究資金を得るためだったり、自身の研究意義を示すためだったりします。
論文で発表する内容の効果が大きいものであれば、話題や注目を浴びます。薬を飲むことで、症状が20%よりも40%改善すると言われた方が、世間的に話題になります。
研究が話題になると、資金の補助を受けやすくなったり、自身の研究に意義があると感じたりしやすくなる。研究者も人間であるため、それなりの事情があるということです。
過失はシンプルに研究者のミスです。データの入れ違いによるミスが代表的です。
一番厄介なのが、自分の望む結果を得るために何回もデータを採取することです。コインの表裏の確率はどちらも2分の1ですが、たまたま5回連続で表が出ることもあります。
その偶然の重なりを利用して、自分の望んだ結果を得ながら研究を進める人も存在します。望んだ結果であれば、自分の研究には意義があると感じ取れます。
研究者が無意識にフィクションを作り出すことがありえるということです。
科学の見極めポイントは再現性!
科学の信憑性で重要なのは、やはり再現性があることです。
再現性が伴わない場合は、前述した内容が絡んでいるということ。
科学的根拠に基づいている情報だから安心だと考えるのでなく、再現性のある科学的根拠に基づいているから安心だと日常生活でも意識しましょう。
実は再現性は科学だけでなく、私たちの日常生活でも重要です。
自分の集中力が高い日、仕事から帰宅してもダラダラせずに行動できた日、気分が良い日などを毎日送れたら将来、人生が充実していきます。
早起きして勉強できた日はなぜかを考え、明日も早起きして勉強して継続するきっかけを見つける。
例えば、寝る3時間前にご飯を済ませていた、寝室の温度が22度だったなど条件を書き出して、再現できるかを試していく。
自分自身の生活を実験していき、再現性を見つけていく感じです。
日常生活で言うと再現性=習慣化とも言えますね。
情報の信憑性や日常生活で再現性を意識して取り入れてみましょう。



コメント